
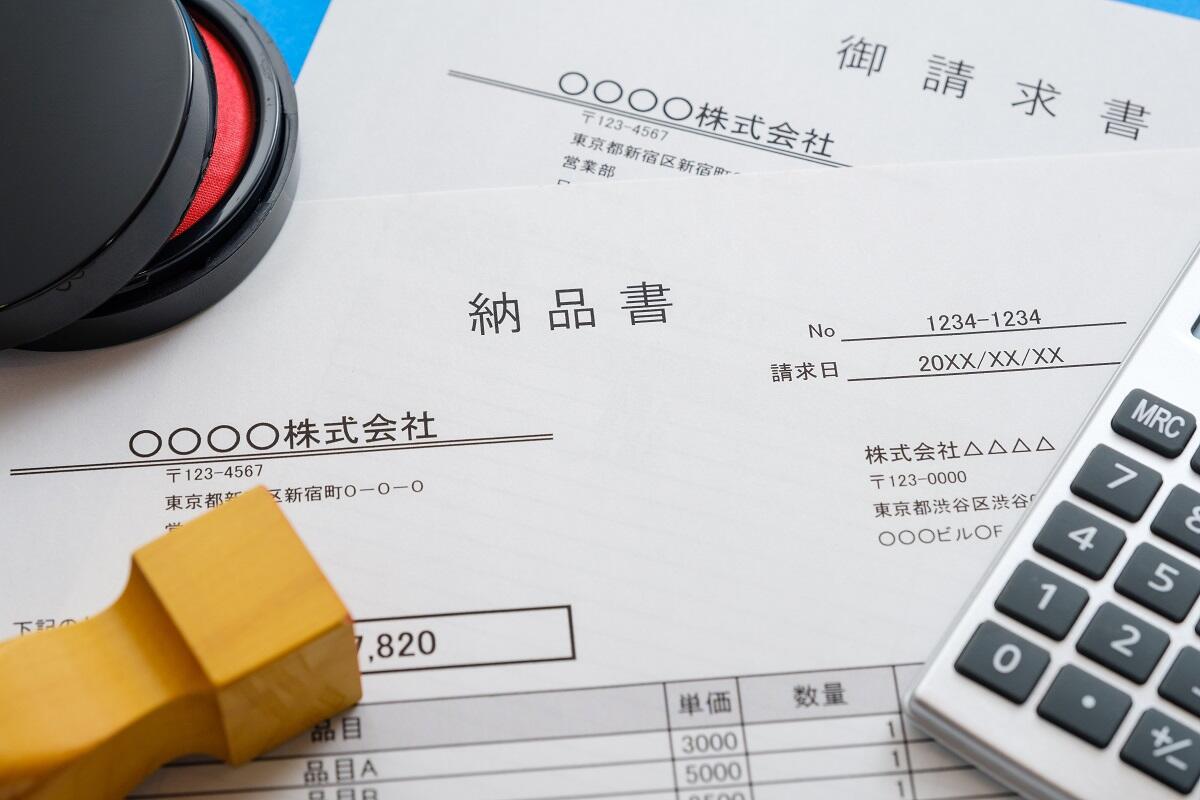
こんにちは。低コストでスピーディに始められる書類保管サービス「WAN-CASE」を提供するNXワンビシアーカイブズです。
納品書は、顧客に提供した商品やサービスの内容を記載した書類です。納品書は証憑(しょうひょう)書類の一種であり、法人税法などによって一定の保管期間が定められています。
会社で納品書を保管する仕事をしている人もいるでしょう。
その一方で「納品書の正確な保管期間がよく分からない」という方もいると思います。この記事では納品書の保管期間や保管方法、電子化して保管する際の注意点などを解説します。
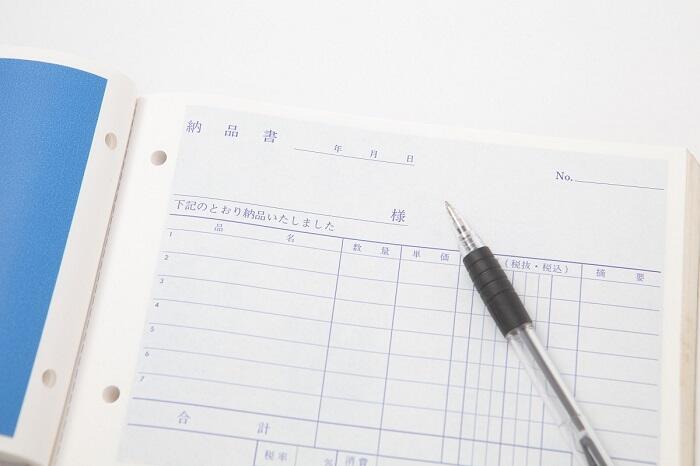
納品書とは、前述したように取引が正確に行われたことを証明する証憑(しょうひょう)書類の一種です。
購入者に物品やサービスを提供する際に一緒に送付したり手渡したりするのが一般的です。
購入者が自分の注文した物品やサービスが正確に揃っているかどうかを確認するための書類で、提供したものの内容や数量、金額を記します。
納品書には作成義務はありませんが、納品書を作製することで購入者に安心感を与え、取引が正確に行われたと証明することができます。
購入者は納品書の品名・品数・値段を確認し、問題があれば報告してくれるでしょう。
何もなければ請求書が発行され、取引は終了です。なお1度だけの購入などの場合は「納品書兼請求書」を発行する場合もあります。
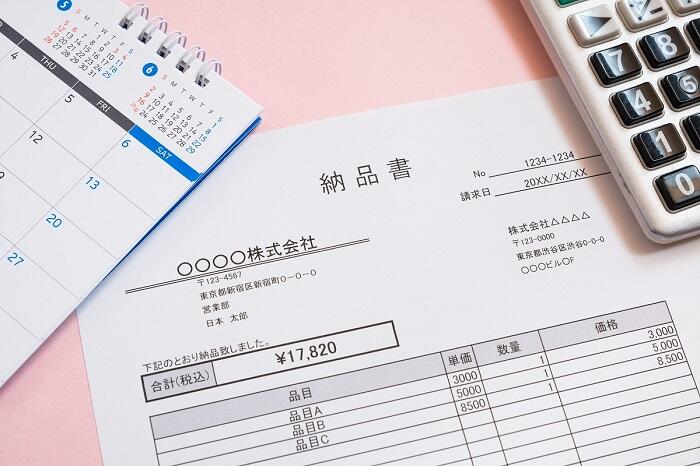
では納品書の保管期間はどのくらいなのでしょうか?
以下に法人と個人事業者の両方の保管期間を説明していきます。
また保管期間の数え方なども解説するので、ぜひ参考にしてください。
法人の場合、「法人税法施行規則第67条の2」によって納品書の保管期限は7年と定められています。
納品書だけでなく、領収書や見積書といった帳簿書類の保管期間は原則として7年です。
もし保管期間中にもかかわらず納品書を破棄した場合、税務調査が入ったときに経費の正当性を証明できなくなります。
その結果、追徴課税が課せられることもあるので、不用意に処分しないようにしっかりと保管しておきましょう。
なお、この7年という保管期間は、納品書が発行された日付から7年ではありません。確定申告の期限日の翌日から数えて7年間です。
3月に決算を迎える企業の場合、提出期限は5月末日です。そのため7年後の5月末日に保管期限を迎えます。3月決算の企業の場合2020年度の納品書の保管期限は、2028年の5月末日になると覚えておきましょう。
赤字決算の場合、青色申告だと「欠損金の繰越控除」を受けられます。
この「欠損金の繰越控除」の期間はかつて7年まででしたが、2008年4月1日以降は9年間、2019年4月1日以降は10年間に延長されました。
2008年~2019年に赤字決算の年がある場合、納品書の保管期限は9年になります。2019年以降に赤字の年があった場合、納品書の保管期間も10年です。
一方で、会社法435条の4では「株式会社は、計算書類を作成した時から10年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない」と定めています。
ですから、会社法に基づくならば、納品書は10年間保管する必要があります。なお、合同会社はその限りではありません。
この保管期間も法人税法と同じく、確定申告の期限日の翌日から数えて10年間です。
※出典:会社法 | e-Gov法令検索
個人事業主の場合、保管期間は5年間です。これは所得税法によって定められています。
個人事業主は法人ではないので、法人税法は会社法の適用は受けません。
また白色申告と青色申告がありますが、保管期間に区別はないので、個人事業主でも5年間は納品書を保管しておくと覚えておきましょう。
ただし、例外は個人事業主のうち、課税事業者として扱われるのは以下の条件を満たしている場合です。
課税事業者の場合は、納品書の保管期間は7年になります。
個人事業主の場合は、確定申告の期限日の翌日から保管期間がスタートします。
確定申告は毎年3月15日ですから、その翌日から年度の保管期間が始まると考えてください。
2019年度、2020年度はコロナ禍の影響で確定申告の期限日が延びました。2019年度の確定申告の期限日は2020年4月16日、2020年度の期限日は、2021年4月15日でした。保管期間も4月からスタートすることになりますので、注意しましょう。
請求書の保管に関しては<請求書の保管期間とは?保管方法や実務の注意点も解説>の記事もご参照ください。
納品書は、法人ならば7~10年、個人事業主ならば5年保管しておくことが義務づけられていることは、お分かりいただけたと思います。
では、納品書はどのように保管すればよいのでしょうか。 ここでは納品書の保管方法について解説します。
従来、納品書は紙の形で保管されていました。
しかし、2022年に電子帳簿保存法が改訂されることに伴い、電子的に作成された帳簿・書類は電子データとして保管する必要が出てきました。一方で、紙の納品書はスキャナーなどで紙の納品書を電子データにする方法が利用されます。
これを「スキャナ保存」といいます。
スキャナ保存をする場合、タイムスタンプの付与や記録事項の入力・訂正・削除など必要な処理をした後、これらの記録を訂正や削除できないシステムで情報の保存を行います。
また、保存場所にパソコン・プログラム・ディスプレイ・プリンター・取扱説明書などを備え付け、画面や書面において整然とした状態で速やかにかつ明瞭に出力できるようにしておく必要があります。
なお、2021年4月1日に、同法が改定され、電子で受け取った納品書は電子のままで保管しなければならなくなりましたが、2021年12月に法改正が発表され、2022年4月1日から2023年12月31日までの2年間は、一定の条件を満たせば電子で受け取った納品書を紙の状態で保管する猶予が与えられました。
国税庁も電子化を推進しています。(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018004-061_01.pdf)
なお基本的に課税期間の途中からは、紙の納品書を電子化して保管するように変更することはできません。
法人ならば事業年度末、決算時期が終わったら、個人事業主の場合は12月31日を一区切りにします。
改ざん防止のための対策にはタイムスタンプを用いましょう。
この手続きをしておけば「自社がコンピュータで作成した納品書の控え」と「取引先から受け取った紙の納品書」をスキャンし電子データなどで保管ができます。
取引先から電子書類の状態でもらった納品書は「電子帳簿保存法第10条」により、電子書類の状態で保管しなければなりません。
一方で、電子書類の状態で受け取った納品書をその状態で保管しておく場合、税務署への届出は不要となり、電子帳簿保存法は緩和されたと言えるでしょう。
納品書を電子化すれば、保管と管理が効率的に行えるようになります。 納品書の確認も短時間で行うことが可能です。
また保管するスペースもとりません。毎月何百枚単位で納品書が発生する仕事の場合、紙で保管していればそのための費用もかかります。
しかし電子書類ならば保管の際にセキュリティを強化でき、保管場所を圧縮することができます。
膨大な量の納品書がある場合、一部が紛失したり盗難されたりしても気付くまでに時間がかかるでしょう。
しかし電子書類ならセキュリティを万全にしておくことで紛失や盗難を防ぐことができます。 万が一火災や地震などの天災が起こっても、納品書が失われる可能性が低くなります。
電子書類を保管する方法はいろいろありますが、クラウドサーバーを利用すれば、万が一パソコンが破損しても、データは無事です。 パソコンを乗り換えてもデータをすぐに移し替えられます。 自社のサーバーに保管しておく場合は、バックアップを複数とっておくと安心です。
納品書を電子保存する場合、紙で受け取った納品書をスキャンし、PDFにして保管する場合と、電子書類の状態で受け取って保管する場合は方法が違うので注意しましょう。
また電子化した帳票は改ざんができないように電子署名やタイムスタンプを押すか、改ざんしたことを記録に残せる方法で保管しておくことが必要です。
さらに電子化した書類は複数の方法で検索できるようにしておかなければいけません。
このシステムを構築するのはなかなか大変です。現在は納品書を電子化し、自動で取引先に送ったり、受領した電子書類を法律に沿って保管するシステムを構築し、提供するサービスを実施している外部業者も増えました。
書類を電子化する場合、信頼できる外部の業者に委託するのもおすすめです。
今回は納品書の保管期間や保管方法を法人と個人事業主に分けて詳しく説明しました。納品書の保管期間は最大で10年です。
今までは紙で保管することが原則でしたが、これからは電子書類の形で保管する方法がスタンダードになるでしょう。

執筆者名 ブログ担当者
株式会社NXワンビシアーカイブズ
ご不明な点やご要望などお気軽にご連絡ください。
ご不明な点やご要望などお気軽にご連絡ください。
