

こんにちは。低コストでスピーディに始められる書類保管サービス「WAN-CASE」を提供するNXワンビシアーカイブズです。
請求書は、取り引きが実際に行われたことを証明する「証憑書類」に分類されます。法律で保管期間が決まっており、勝手に処分することはできません。
その一方で、「保管期間の正確な年数がよく分からない」という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、法律に基づく請求書の保管期間や保管する際の注意点、さらに電子化して請求書を保管する方法などを解説します。
請求書の管理方法について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
請求書とは、商品やサービスを提供した際に代金を請求する書類です。
前述したように取り引きが実際に行われたことを証明する「証憑(しょうひょう)書類」に分類され、法人税法・所得税法・消費税法などによって保管期間が決められています。
勝手に処分することはできません。
なお、請求書の保管義務があるのは「他社から受け取った請求書」です。 自社で発行した請求書の場合、控えを作成しているならばそれを法律で定められた期間保管しておくと税務調査が行われたときも安心です。ただし、請求書の控えを発行する義務はないため、作成していなくても問題ありません。
保管する義務があるのは「受け取った請求書」と覚えておきましょう。
なお、受け取った請求書は必ず原本を保管しておきます。汚れたり破損したりしてもコピーを取って原本を捨ててしまうと請求書の偽造や不正会計が行われたと疑われる可能性があります。コピーを取った場合も必ず原本は保管しておきましょう。
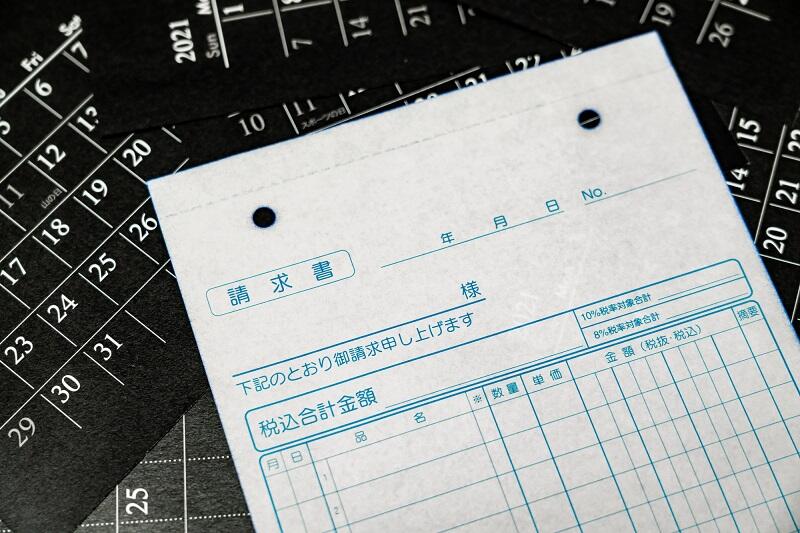
はじめに、法人が請求書を保管しなければならない期間について解説します。
基本と例外がありますので、よく覚えておくことが大切です。
法人における「請求書」は、法人税法で7年間と定められています。
保管期間のスタートは、事業年度の確定申告書の提出期限の翌日からです。
例えば3月決算の場合、確定申告書の提出期限は5月末日ですから、6月1日から7年間保管義務があります。請求書発行された日から7年間ではないので注意しましょう。
また青色申告をしている場合、決算が赤字の際には「欠損金の繰越控除」を受けられます。
この「欠損金の繰越控除」の期間はかつて7年まででしたが、2008年4月1日以降は9年間、2019年4月1日以降は10年間に延長されました。
つまり、2008年~2019年4月1日の期間で決算に赤字の年があった場合は9年、2019年以降赤字の年が会った場合は10年間請求書を保管しておかなければなりません。
念のため請求書10年間保管しておくようにすれば、税務調査が入っても安心でしょう。
次に個人事業主が請求書を保管しなければならない期間について解説します。
法人に比べてどの程度差があるのでしょうか。
個人事業主の場合、所得税法によって保管期間は5年と定められています。
領収書が青色申告、白色申告で差があったのに対し、請求書は差がありません。両方とも5年です。
なお保管期間の数え方は確定申告の期限日から数えて5年間です。
2020年、2021年の確定申告の期限日はコロナ禍のために延びましたが、通常は3月15日です。1月1日~12月31日までに受け取った請求書は、その年度の確定申告の締め日である3月15日の翌日、3月16日から5年間保管しておきましょう。
請求書が発行された日付ではないので間違えないようにしてください。
個人事業主の場合、以下の条件をどちらかでも満たしているときは、消費税の納税が必要です。
そして消費税の納税義務者の場合、請求書の保管期間は7年です。
なお個人事業主で消費税の納税義務者の場合は、ほぼ全てが青色申告をしていることでしょう。
青色申告の場合、帳簿書類を7年間保存することが定められています。青色申告の場合は念のために7年間受け取った請求書を保管しておきましょう。
保管期限が来る前に請求書や領収書を廃棄してしまうと、それを理由に青色申告の承認を取り消されてしまう事もあるため注意が必要です。
前述したように5~7年の保管義務があるのは他社から受け取った請求書だけです。
自社で発行した請求書の控えの作成義務はありませんが、作成している場合は、法律で定められた保管期間の保存の義務はありますので、ご注意ください。
なお、請求書を受領しても、以下の記載がないと消費税の仕入税額控除を受けられません。ですから、請求書を発行する方も以下の5項目の記載をしておきましょう。
引用:国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6625.htm)
記載事項が満たされていないと、正式な請求書を認められないこともありますので気をつけましょう。
ただし、小売業、飲食店業、タクシー等を営む事業者が交付する書類は、5. を省略することができます。
インボイス制度とは、2023年(令和5年)10月1日から始まる「適格請求書等保存制度」のことです。
この制度が始まると、認定を受けた事業者が発行する適格請求書のみが仕入税額控除の対象となります。(一部例外あり。3万円未満の公共交通機関など)は対象外)
認定業者になるためには課税事業者になる必要があります。 そして、重要なのはインボイス制度がはじまると請求書を発行した側も7年間の請求書の保管義務が生じます。
今まで保管が不要だった発行する方も保管義務が生じるので、注意しましょう。
法人も個人事業主も関係なく請求書を発行する側、受け取る側すべてが対象になります。 なお、保管期間のスタートはこれまでと変わりありません。確定申告の期限日の翌日からです。

では、請求書はどんな方法で保管しておくのが望ましいでしょうか?ここでは請求書の保管方法と注意点を解説します。
書面での保管方法は最も基本的な方法です。長年書面で請求書を保管してきたので、これからもその方法を行うという企業も多いでしょう。
書面での保管は送られたものをそのまま保管すればいいので、手間がかかりません。
ただし保管場所を取るデメリットも。
請求書が年に数百枚程度ならばそれほど大量な書面の量にはなりませんが、大企業の場合は、年に数万枚の請求書を受け取るところも珍しくありません。
これらをすべて項目ごとに分けてファイリングし、7年~10年取っておくのは大変です。 また、請求書は税務署から要求があった場合はすぐに出せるようにしておかなければなりません。
ファイリングまでは膨大な手間はかかりますが、検索がしやすい状態にすれば、管理の手間は減ります。
なお、ペーパーレスが進んでいるので、これから紙の請求書はどんどん減っていく可能性があります。なお、紙の請求書を電子保管する場合は、電帳法による制約があるので、十分に注意するようにしましょう。(参考:記事「電子帳簿」保存」
電子帳簿保存法(電帳法)という法律に基づき、紙の請求書も電子データで保管することが可能になりました。電子データでの保管には電帳法の条件を満たす必要があります。
1については、2022年1月1日より電帳法が改正され、届出は不要になりました。
最近では請求書を電子で発行したり、電子データを保管するサービスを提供する業者も増えています。
国税庁は発行する「始めませんか、帳簿書類の電子化」というパンフレットの中で「自己がコンピューターを使用して作成した帳簿」は電子データのまま保存可能と記載されています。これは、パソコン(電子)で作成され、受領側はメールに添付される、もしくはWEBサイトからダウンロードなどの方法で、送付された帳票です。なお、電帳法の改正により2022年1月1日より原則、電子で送られた帳票は電子データの状態で保存しなければなりません。
(*)現在は、2022年4年1月1日より2年の紙保存可の経過措置が講じられています
「自己がコンピューターを使用して作成した帳簿」とはパソコン等のソフトを使用して作った書類を意味します。
請求書の控えも、電子データとして保管しておくことが可能です。
インボイス制度が導入されれば、請求書を発行した方も控えを7年間保管しておく義務が生じます。
但し、改編ができないシステムを用いて運用されていることなどクリアする条件があります。
詳しくは国税庁が発行するパンフレット「始めませんか、帳簿書類の電子化」を確認しましょう。
現在でも、請求書の控えを発行している場合は、保管義務があります。(電帳法第10条)
請求書控えを発行せずに、社内システムなどで入金管理ができているなど、請求書控え自体を発行していない場合は、現在の法律では、請求書発行側に保管義務はないですが、2023年10月1日から始まる「インボイス制度」により適格請求書の発行側も、保管義務が生じます。
前項でご紹介した国税庁のパンフレットに記載してある条件を満たせば、請求書を電子化して保管しておくことが可能です。
なお、紙をPDF化やデジタルカメラで撮影して電子化した場合、タイムスタンプを付与しておけば、紙の原本は破棄が可能です。
ただし、ヒューマンエラーでタイムスタンプが押していなかった場合などを考え、年に1度の割合で定期検査を行い、間違えがなかったらそこで原本を破棄するなどの内部システムを作っておくといいでしょう。
電子化して保管をすることは、ペーパーレス化を進めるのにも適切な方法の一つと言えます。(https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_03.pdf)
「電子帳簿保存法第10条」により、電子取引における取引情報の保存が定められています。
電子取引とは、以下のようなものを指します。
現在、多くの企業がこのような方法でやりとりを行っているでしょう。
取り引き情報の中には請求書も含まれています、
電子取引の請求書は、電子帳簿保存法施行規則における保存要件-第3条によって、
つまり、電子上で請求書を保管しておく場合は検索が容易ですぐに見せられる場所に保管しておき、尚且つ改ざんが不可能な状態でなければならないということです。
難しく思えますが、今はそのシステムを組み込んだ請求書の自動保存サービスなども提供されていますのでそうしたサービスを検討してみましょう。
現在は、書面もスキャナーや写真撮影などで簡単に電子化できるようになりました。
しかし、電子化したデータをフォルダーに入れておくだけでは、「請求書の原本」として認められません。
国税局の「始めませんか、帳簿書類の電子化」などのパンフレットを参考に、国税庁が「請求書の原本」として認められる体裁を整えることが電子化の第一歩です。
理想は、取引先と同時に電子化を行い、既存の取引書類の電子化サービスなどを利用することです。
これが難しい場合は、紙の書類のPDF化などのマニュアルを作り、社員教育を行って正確に書類を電子化できるようにしておきます。
このほか、紙の原本の破棄時期の設定や外部に電子化された情報が漏れないためのセキュリティ強化も重要です。
必要ならば、請求書を発行できるパソコンを限られたものだけにしておき、接触できる社員を限りなどの対策も必要になります。
この記事では、請求書の保管期間や保管方法について解説しました。 受け取った請求書は最長で10年の保管が必要です。 また、インボイス制度が始まると、請求書を発行する側も7年の請求書保管が定められています。
請求書の電子化は今後ますます進みますが、紙書面の保管も当面残る可能性はあり、保管スペースの課題がでてくるでしょう。その場合は、外部倉庫保管の利用も解決策の一つです。NXワンビシアーカイブズの書類保管サービスを検討ください。

執筆者名 ブログ担当者
株式会社NXワンビシアーカイブズ
ご不明な点やご要望などお気軽にご連絡ください。
ご不明な点やご要望などお気軽にご連絡ください。
